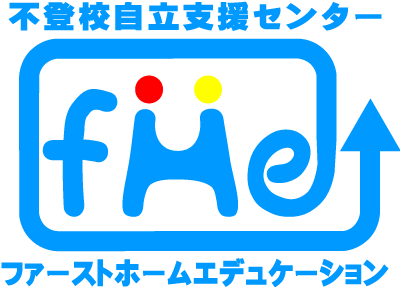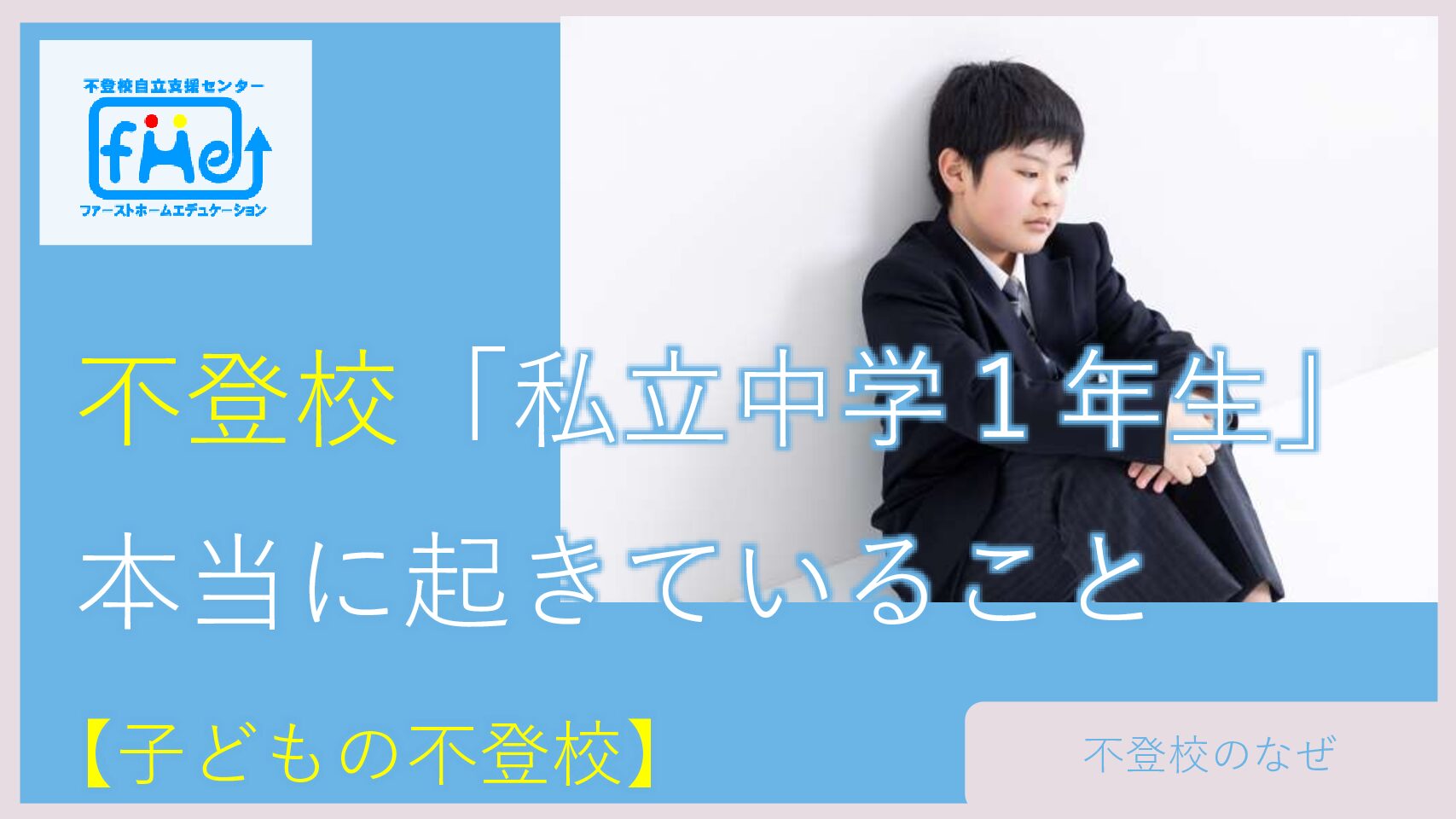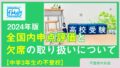私立中学1年生の不登校:見落とされてきた本当の理由と対応のポイント
「うちの子だけ……?」
「せっかく私立中学に合格したのに」
私立中高一貫校に入学した中学1年生が、わずか数週間〜数か月で登校できなくなる。
今、そうしたご相談は、ここ数年で確実に増加傾向にあります。
「燃え尽きたのかも」「まだ慣れていないだけ」──
多くの親御さんがそう考えます。
しかし私たちは、私立中学校の復学支援に長年携わってきた、臨床経験豊富な心理職チームです。
ただ話を聞いてきたわけではありません。
すべてのケースに、心理職による徹底したアセスメント(専門的分析)を行ってきました。
支援の積み重ねのなかで、ある共通した傾向が徐々に明らかになってきました。
中1で不登校になる多くの子どもたちは、小6の受験期ですでに限界に達していた──
合格と同時に終わるサポート。始まる自己管理。
崩れていく“優等生”というポジション。
「やっと終わった」と思った矢先に、始まる“新たなレース”。
本記事では、どこでも語られてこなかった不登校の本質と、
「誤った理解が、誤った支援を生む」──その二次被害を防ぐために、
今こそ知っていただきたい“正しい見立て”と支援の道筋を、現場からお伝えします。
第1章:中学受験後に増える?私立中学1年生の不登校の実情
「私立中学に入ったばかりなのに、もう登校できない…」
そんな相談が、年々増えています。
文部科学省の令和5年度調査では、不登校の児童生徒数は全国で34万6,482人にのぼり、中学生だけで21万6,112人と、過去最多となりました。
特に「中学1年生の春」に不登校が集中する傾向が見られ、支援現場でもその傾向が実感されています。こうした傾向は、研究機関や自治体の報告でも裏づけられています。
中1の1学期に不登校が集中して始まる
国立教育政策研究所が行った全国調査によって、小学校6年生から中学1年生への進級を追跡しました。その結果、不登校の発生が最も多いのは「中学1年生の1学期」であることが明らかになっています。
この時期は生活環境や人間関係が大きく変わるため、多くの生徒が戸惑いや不安を抱えやすい時期でもあります。
出典:
国立教育政策研究所「中1不登校傾向に関する調査研究」(研究紀要 第138集)
https://www.nier.go.jp/a000110/kiyou138-16.pdf
「進級・入学時の不適応」が主要要因に
さらに、国立成育医療研究センター「不登校白書2023」でも、不登校のきっかけとして、「入学・進級時の不適応」が中学生全体の5.8%にを占めることが報告されています。
この数字は、生活環境や人間関係が大きく変わるため、多くの生徒が戸惑いや不安を抱えやすい時期でもあります。
出典:
国立成育医療研究センター「不登校白書2023」
https://www.ncchd.go.jp/center/activity/kodomo_thinktank/pr/ima02.pdf
私立中学でも「中1春の不登校」は多い
こうした傾向は公立中学だけでなく私立中学にも共通しています。FHEに寄せられる支援依頼でも、「私立中1・入学後すぐ」の不登校はとても多くあります。
特に4〜6月の相談が集中しており、これは単なる“燃え尽き”では説明しきれない、構造的な原因があることがうかがえます。
次章:見逃されてきた「本当の原因」とは
これまで「受験疲れ」や「春先の変化によるストレス」と捉えられてきた私立中1の不登校ですが、
しかし、私私たちが20年以上にわたって現場で支援してきた経験からは、それだけでは説明のつかない実態が数多くあります。
次章では、多くの専門家が見落としている「本当の要因」──小6時点ですでに始まっていた受験不適応と、それが中学入学後にどう連鎖していくのかについて支援現場の視点から具体的に解説していきます。
第2章:よくある見立てでは足りない──「燃え尽き」だけでは説明できない
「中学受験の反動で、うちの子は燃え尽きたんです」
私立中学1年生の不登校に関する相談では、こうした言葉がよく聞かれます。確かに、過酷な中学受験を乗り越えたあとに一気に力が抜けてしまう「燃え尽き」は、珍しいことではありません。
しかし、実際の支援の現場では、その説明だけではどうにもつじつまが合わないケースに頻繁に出会います。
「燃え尽きた」では説明できない現実
たとえば、「最初の1週間で学校に行けなくなった」ケース。クラスにさえ馴染む前に、早々に欠席が始まっているのです。
また、「友達もできて、最初は楽しそうに通っていたのに、GWを境に急に行けなくなった」ケースもよくあります。
これらの子どもたちは、決して「やる気がない」「学校に適応できなかった」と単純には言えません。むしろ、多くの子どもたちは、限界まで努力した上で不登校に至っていることが多いのです。
受験を終えた達成感と反動“だけ”ではない
「受験で出し切ったからこそエネルギーが切れてしまった」という見立ても、表面的には当てはまるかもしれません。しかしそれだけでは、その後の不登校の長期化や本人の自己否定感の強さを説明することができません。
そもそも中学受験は、単なる努力ではありません。塾が管理する学習スケジュールに従い、親がサポートし、子どもは「言われたことをこなす」形で進むことが多いのです。
この「外部管理型」の勉強スタイルから、「自分で計画、管理して進める」中学の学習スタイルに切り替わる中で、つまずく子は非常に多く見られます。
“適応できなかった”という見立ての危うさ
「うちの子は人間関係が苦手だから」「もともと内向的だったから」という保護者の見立てもよく聞きます。
ですが、内向的な子どもがみんな不登校になるわけではありません。自分が内向的であることを理解している子どもは、クラス内で自分のポジションを上手に見つけていくこともあります。
問題になるのは、「こうありたい」という理想像と、現実の自分との間にあるギャップです。
特に、「小学校では成績が常に上位だった」「塾では優等生だった」など、高い評価を受けていた子が、レベルが高い集団に入って「普通」の存在になることで、大きな戸惑いと無力感を抱えることがあります。
「時期ごとのパターン」に注目する重要性
中学1年生の不登校には、「いつ休み始めたか」によって、見立ても対応も大きく異なります。
たとえば、入学直後に欠席が始まった子と、夏休み明けに欠席する子では、抱えているものがまったく違います。
にもかかわらず、「とりあえずフリースクール」「とりあえず本人の様子を見よう」といった“一律の対応”がされてしまうことも少なくありません。
重要なのは、子どもが「どのタイミングで」「どういう経緯で」不登校に至ったのかを丁寧に把握し、それに合った見立てをたてることです。
次章では、これまでの支援事例をもとに、不登校の背景にある「構造」をできる限りわかりやすく整理してお伝えします。
第3章:誰も語らなかった“本当の原因”──私立中1の不登校の構造
私立中高一貫校に通う中学1年生の不登校は、「燃え尽き」や「適応の失敗」といった言葉では語り尽くせない、もっと深くて複雑な構造を持っています。
この章では、私たち支援者が20年以上の実践から見出した、本当の背景と構造を5つの視点で整理してお伝えします。
他の記事にはほとんど書かれていない「根本的な要因」に目を向けてみてください。
1. 小6の受験期にすでに限界だった
中学校に入ってから不登校が始まったように見えるケースでも、実は小学校6年生、受験期の段階ですでに限界が近づいていたケースが少なくありません。
・長時間の塾通いと、親による徹底管理
・「勉強だけがすべて」という生活リズム
・閉じられた人間関係
このような生活を1〜3年続けると、「頑張っていたけど、心はすでに限界」という状態になりやすいのです。
中学入学という「切り替えのタイミング」で、その限界が表面化するケースが見られます。
2. 勉強が“自己管理”に変わる壁
受験期の勉強は、ほとんどが「塾」や「親」によって管理されています。
スケジュールもペースを周囲が決めてくれる。
しかし、中学校に入ると「やるべきことを締め切りから逆算して自分で進める」学習スタイルに変わります。このギャップに戸惑い「課題を溜めて」しまったり「計画しても実行できない」と感じる子どもが少なくありません。
「自分は自分のことをコントロールできない」という現実に直面し、自信を失いそこから勉強がイヤになってしまうこともあります。
3. “できる子”のアイデンティティ崩壊
中学受験を通して「私は賢い」「周りよりできる」という自己イメージを持ってきた子どもたちは、私立中学に入学した途端、その「特別さ」が失われていきます。
・小学校では当たり前だった「上位の成績」が通用しない
・以前は特別だったのに、今は「普通」になってしまった
・勉強だけでなく、人間関係でも“目立たなくなる”
こうした変化は、「今までの自分の存在意義がなくなった」と感じるほどのインパクトを与えます。
4. 「これからが本番」と言われる現実
私立中高一貫校は、6年間で大学進学を目指す長期的なカリキュラムが組まれています。
中学受験を終えて「やっとひと段落」と思った子どもにとって、入学直後から「ここからが本番」と言われ、学習のペースも加速することは大きなギャップとしてのしかかります。
・朝学習、7時間授業、頻繁な小テスト
・家でも課題に追われて休めない
・長い通学時間による疲労
このギャップに絶望し、「まだやるの?」「もうついていけない」と感じる子どもが出てくることは自然なことともいえます。
5. ポジション喪失──上には上がいる世界
小学校では「勉強ができる子」「先生に評価される子」など、明確なポジションを持っていた子どもも、
私立中学校ではその立ち位置を失うことがあります。
・「自分はできると思っていたのに、もっとできる子がいる」
・「前は注目されていたのに、今は誰からも見られていない」
・「どこにも自分の居場所がないように感じる」
この「ポジションの喪失」は、子どもの自信と意欲を大きく奪います。
専門家としての結論
私立中1の不登校は、目のまえの出来事だけを見誤ってしまいます。
その多くは「小6〜中1前半までの経験」の積み重ねの中で、静かに進行してきた「構造的な問題」です。
目に見える不登校という「結果」の裏側にある「連続した過程」をきちんとアセスメントすることが支援の第一歩になります。
次章では、こうした背景がどのような「行動」として現れ、不登校へとつながっていくのか、
具体的なパターン別にご紹介します。
第4章:私立中学1年生の“不登校の始まり方”──時期ごとに異なる4つのタイプ
不登校と一口にいっても、「いつから休み始めたのか」によって背景や対応の考え方が大きく異なります。
ここでは、私立中学1年生の支援現場でよく見られる典型的な4つの「始まり方」を注目し、それぞれの特徴とポイントをお伝えします。
【タイプA】入学直後〜4月中に始まる不登校(入学即・早期欠席型)
特徴
・入学してすぐに違和感を抱き、数日〜2週間以内に欠席が始まる
・クラスや人間関係を十分に経験する前に登校が止まる
・「緊張が強すぎる」「最初の一歩が出ない」「怖い」などの表現も多い
背景の例
この時期に休み始める子どもたちは、「中学に適応できなかった」というよりも、そもそも“入っていない”という感覚のほうが近いかもしれません。
小学校6年生の中学受験期にすでに受験不適応が起きていたケースや、第一志望校ではない学校への進学だったケース、「最初のポジション取り」がうまくいかなかったケースなどが含まれます。
【タイプB】5月初旬GW明け〜夏休み前に始まる不登校(反動型・評価崩壊型)
特徴
・5月初旬(GW明け)〜6月頃にかけて、急に欠席が始まる
・最初は順調に見えていいたが、突然「行けない」と訴え出す
・担任からも「むしろうまくやっていた」という評価をされることも多い
背景の例
一見適応しているように見えながらも、実は最初から「がんばる気持ち」が薄かったケースもあります。
「話しかけられたいけど、自分からはいけない」といった、理想と現実のズレに苦しんでいた子どもが、
クラスの関係性が固まっていく中で、「もう理想の居場所はできない」と感じてしまうことも。また、「もっとできるはずなのに結果が出ない」といった自己評価の崩れが引き金になることもあります。
【タイプC】夏休み明けに始まる不登校(リセット・拒絶型)
特徴
・夏休みが終わる直前〜9月初旬の登校再開時に登校拒否を示す
・「宿題がおわっていない」「休み明けがしんどい」と訴える
・新学期の準備をするだけで気持ちが重くなってしまう
背景の例
このタイプでは、夏休み中に「行きたくない気持ち」が強まってしまったケースが多く見られます。
学校生活の中で何となく違和感を抱えながら過ごしていた子どもが、長期の休みのあいだに不安や避けたい気持ちを抱え込んでしまい、それば「戻れなさ」に変わっていくのです。
また、夏休み明けの時期というのは、部活動と勉強との両立に難しさを感じ始める子どもや、小学校での不登校経験がある子どもがペースを崩すタイミングでもあります。
【タイプD】3学期・学年末に欠席が始まる(崩壊・フェードアウト型)
特徴
・2月〜3月、学年の終わりに欠席が始まる
・それまで何とか登校していたが、最後に力尽きてしまう
・「あと少しだったのに」と感じられる状況で休みが始まる
背景の例
このタイプは、「1年間がんばったけど、やっぱり限界だった」というフェードアウト型。
周囲からは「このまま乗り越えられるのでは?」と見られていた子が、最後の一歩がどうしても踏み出せなかったというケース。
成績や学業との関連の欠席が多く見られる時期。急激な成績低下があるわけではないものの、「得意なはずだったことがうまくいかない」など、本人の中での違和感が積もって限界を迎えることがあります。
なぜ「始まり方」が大切なのか?
私たちFHEでは、単に「不登校」というラベルではなく、「どのように始まり、どの段階で止まったのか」という点から見立てをたてることを重要視しています。
・タイプAは、まだ適応の舞台に立てていない
・タイプBは、表面的な順調さの裏で自己評価が崩れた
・タイプCは、休みのあいだ不安が増幅された
・タイプDは、努力をしてきたが力尽きた
それぞれの背景を知ることで、見える世界も、取るべき対応も変わります。
このあとの第5章では、保護者の方が「よかれと思ってやってしまいがち」だけれど実は支援を難しくしてしまう行動を、ランキング形式で紹介していきます。
第5章:藤本先生に聞いた「それ、する前に相談してほしかった」不登校対応ランキング
不登校が始まったとき、多くのご家庭では「何かしてあげなきゃ」と思い、善意からさまざまな対応を取ろうとされます。しかし、支援の現場では「その前に相談してもらえていたら…」と感じる場面が少なくありません。
ここでご紹介するのは、「正しくない対応」ではありません。アセスメントがやや不足していた場合、結果として子どもの状態を複雑にしてしまいやすかった対応です。
ご家庭の「想い」と、子どもの「状態」にズレがあると、意図に反して、子どもの状態が不安定になることもあり、思いとは裏腹に、状態が長引くこともあります。
以下では、実際の支援現場でよく見られる「結果として支援が難しくなりやすかった対応」を、ランキング形式でご紹介します。
※「もしかして、うちもそうだったかも…」と感じた方も、大丈夫。私たちは支援の現場で何度も、そこから立ち直っていくご家庭を見てきました。どのケースも、ここから整えていくことができます。
第1位:退学してしまった
起きやすいズレ
「もう行かない」と本人が言い、ご家庭が退学を決断するケースがあります。とくに、学校側からもネガティブな対応や言葉があった場合、保護者は「このまま在籍させても仕方がないのでは」と感じてしまうことがあります。
しかし実際には、私たちが関わってきた支援の中でも、そうした言葉が一時的な感情や自暴自棄の中で出たものであったケースは少なくありません。きちんと気持ちを整理していく過程で、元の学校に戻りたいという選択をした子どもたちが多くいました。
リカバリのヒント
退学、転学とという選択をしたあとも動きだせないままの場合は、「自分で前を向いた」という納得感のない移動が回復を難しくしていることがあります。
退学は終わりではなく、新しい選択肢を考える準備期間です。退学、転学をしたが回復できていない場合
- 本人の強い意思だったか、親が促して同意を得た形か
- 転学後の学校へ登校はできたか、できなかったか、どの程度登校したか
- 転学後のイメージは良いイメージ持てていたか、期待とのズレがどこにあったか
これらを整理し直すことで、次に進む道が見えてくることがあります。今の状況を整理していくことが大切です。「どうしたらいいかわからない」と感じたら、一人で抱え込まず、整理のサポートを受けてください。
第2位:家庭教師をすぐに入れてしまった
起きやすい反応:
「せめて勉強だけでも」と思い、家庭教師を導入した結果、子どもが「またやらされる」と感じて拒否的になってしまうことがあります。特に受験で消耗した後のタイミングには注意が必要です。
リカバリのヒント:
もしお子さんがストレスや拒否感を見せているなら、いったん勉強から離れても構いません。「勉強=苦しいもの」という思い込みを変えるには、学びを“自分のため”に感じられる機会をつくることが第一歩です。焦りを感じられると思いますが、支援の現場では復学後に継続登校がしっかりできてから、勉強に向き合うようにプログラムを組むことが一般的です。
第3位:ゲーム・スマホの使用が大幅に増えてしまった
- 昼間の使用時間
- 夜間遅くの使用時間
- 長時間使用
上記のチェックポイントの中で一番気になるところから、本人と話し合いをする機会を取ってみましょう。
第4位:自室で食事を完結させてしまった
- 夕食だけは一緒にとれるようにする
- デザートやお菓子を一緒に食べないか誘う
- お茶を飲みに来た時に興味のありそうな映画などをつける
関わりのハードルが低いもので構いません。家庭という場で“つながり”を感じられる時間を育てていきましょう。
第5位:「学校という環境はうちの子には合わない」と決めつけてしまった
「この子にとって、無理なく社会とつながる方法は何だろう?」
一度「学校は合わない」と感じたとしても、それが「すべて」ではありません。もう一度、学校という場と向き合える方法を探していく中で、子どもは少しずつ「戻ってみようかな」という気持ちを取り戻すことがあります。
「変われるかもしれない」その小さな希望を、一緒に育てていきましょう。
第6章:よく似て見えるけれど違う──私立中1不登校の3つのタイプ
※この章に登場するエピソードは、支援現場の経験にもとに、守秘義務に配慮して一般化内容です。
まず知ってほしい「同じ中1不登校」でもタイプは違う
「中1になってすぐ不登校になった」と聞くと、多くの人は「環境に適応できなかったのかな」「受験の燃え尽きでは?」といった、ひとつの理由に絞って考えてしまいがちです
しかし、実際の支援現場では「同じように見える不登校」であっても、その背景や支援の方法は異なる場合が多くあります。
この章では、私立中学1年生の不登校でよく見られる「3つのタイプ」を紹介し、それぞれの背景や支援の違いを整理していきます。
タイプA:最初から孤立していた「ポジション不在型」
入学直後、ほとんど学校に通えないまま不登校になるこのタイプは、いわば「スタート以前から欠席する芽ができていた」状態です。
クラスの中で「居場所」を作るきっかけが持てず、自分から話しかけられない、関わりたいけれど動けないという状態が続き、「どうして誰も声をかけてくれないのか」と孤独を感じていきます。小学校では環境に恵まれ、特に困ったことがなかった子ほど、こうした変化に戸惑いやすい傾向があります。 このタイプへの支援では、安心できる環境の中で、少しずつ「関わり」を取り戻すことが大切です。
タイプB:夏休み明けに崩れた「自己管理移行失敗型」
最初は学校生活に馴染んでいて見えたのに、夏休み明けから登校が難しくなるこのタイプ。
背景には、受験時代の「塾や親に管理されていた学び」から、「自分で管理する学習」への移行がうまくいかなかったことがあります。
課題が進まない、生活リズムが崩れた、自分を律せない…良くないなと自分でも感じていても、どう直していいのかがわからない。「やっていない自分」に対する罪悪感だけが膨らみ、やがて「行けない」に変わっていきます。
このタイプでは、「自己管理できる力」を育てるより前に、まずは「自己管理する意識そのもの」を構築することが求められます。
支援では、「どこがどう止まっていたのか」を本人と一緒に点検し、再構築できる感覚を育てることが鍵となります。
タイプC:三学期に突然休む「過剰適応・仮面崩壊型」
半年以上、まったく問題がないように見えていた子が、年明け以降に突然登校できなくなる。
表面的には「しっかり者」と見えますが、内面では無理を重ねてきた「過剰適応型」です。
「こう見られたい」というイメージを保とうと努力するうちに、自分の本音が押し込められ、心身が限界を迎えてしまうのです。 このタイプへの支援では、「自分らしさ」を取り戻すことが第一歩となります。。
このタイプの支援では、「自分で作ったセルフイメージ」が自分を苦しめていたことに気づくことが第一歩。
「こう見られたい自分」と「楽な自分」とのギャップに気づき、セルフイメージを少しずつ変容させていくプロセスが不可欠です。
“似て非なる3タイプ”の支援の違いとは?
これら3つのタイプは、いずれも「私立中1で不登校になった子」ですが、その背景や必要な支援は大きく異なります。
共通しているのは「努力不足」ではなく、「自分を客観視する力の未発達」
たとえば──
- 「学校がつまらない」=クラスが合わない
- 「友達ができない」=自分が内向的だから
- 「この学校は向いていない」=ほかの環境ならうまくいく はず
このように、自己理解がまだ浅い段階での「思い込み」が強まることで、不登校が続いてしまうことがあります。
親御さんもまた、子どもの言葉をそのまま受け取り「やっぱりこの子には学校が無理なのかも」「性格的に集団は向いていない」と感じてしまうことが少なくありません。
本当の“きっかけ”を見つけるために
私たちは、20年以上にわたり、こうした「似ているけれど違う」ケースを丁寧にアセスメントしてきました。
子どもの言葉や態度の背景にある「見えにくいサイン」を見つけること。 それが、支援の方向性を決めるカギになります。ご家庭で見極めるのが難しいときは、遠慮せず専門家にご相談ください。
次章では、実際に訪問支援で、どのように子どもたちが再び動き出すのか、そのプロセスをご紹介します。
第7章:動けない子どもと向き合う──訪問支援の現場から
アウトリーチ(訪問支援)「学校に行けない」というより、「家から出られない」。そんな状態にある中学1年生の不登校には、訪問支援(アウトリーチ)が必要になることがあります。
動けない子どもへの支援では、最初から家庭に関わる訪問支援が効果的なことも多く、これは就労支援の場面でも共通しています。つまり、訪問支援は「最後の手段」ではなく、「はじめの一歩」として選ばれるべきものだと、私たちは考えています。
訪問支援の第一歩は「見立て」と「アセスメント」から
多くの支援で見落とされがちなのが、「本当は何が子どもを止まらせているのか」というアセスメントの視点です。
子どもが話している内容だけでは、状況を正しく把握することは難しい場合があります。 心理職による観察や家庭環境の把握・理解を通じて、的確な支援の方向性を探っていきます。
FHEでは訪問カウンセラーと教育的コーチングを組み合わせ、「本人が気づけていない障壁」を丁寧に見極めながら支援計画を立てていきます。
「やる気を引き出す」支援には、経験と技術がいる
最近では「不登校コーチング」という言葉も見かけるようになりましたが、FHEが導入しているのは、心理職が実施する「教育的コーチング」です。
一時的な関わりや「励まし」ではなく、自己決定・自己理解・自己管理の3つの力を再構築するための支援であり、数ヶ月単位の継続的な関わりが必要です。
表面的な目標設定ではなく、「この子が本当に大切にしているものは何か」を共有しながら、「やる気」だけではなく「納得」をつくることを育てていくことを重視しています。
「正論」よりも、「動き出せるきっかけ」を
動けない状態にある子に「頑張ろう」は通じません。大切なのは「頑張る気持ち」が自然に湧いてくるシステムと関わりです。FHEの訪問支援では、まず教育的コーチングを通じて、本人が「自分も頑張ってみよう」と思える気持ちを引き出します。
その上で、訪問カウンセリングにより、その「頑張ろう」という気持ちを支えながら、実際の行動に結びつけていきます。
このプロセスを通じて、子どもは「支えてもらったけど、自分の力で乗り越えた」と実感できるようになります。
そのプロセスは、就労支援のひきこもり回復のプロセスと同じで、段階的な支援計画と納得を軸とした介入が必要です。中学1年生の不登校において、これは決して「過剰な介入」ではなく、「必要な一歩」です。
ゴールは「社会とつながる力」を取り戻すこと。
再登校がすべてのゴールではありません。FHEの支援は、子どもがもう一度「自分らしく社会とつながっていける力」を取り戻すことを目指しています。
よくあるご質問:私立中学1年生の不登校について
1. 中学受験後すぐに不登校になるのはよくあること?
はい、実際に非常に多くのケースが報告されています。多くは「燃え尽き」ではなく、中学受験の段階ですでに心理的な限界に達していたケースです。中学校そのものの問題というより、受験期の過剰な負荷やポジション喪失が背景にあることが多く見られます。
2. 「私立中学が合ってない」と子どもが言ったら転校を考えるべき?
すぐに転校を考えるよりも、まずは専門家による「見立て」が必要です。不登校の背景にあるのは環境の不適合よりも、「適応できなかった経験の意味づけの失敗」であることが多く、環境を変えるだけでは根本的な解決にならないことがあります。
3. 不登校中に家庭教師やタブレット学習を始めてもいい?
学習の遅れが気になる気持ちはわかりますが、本人の気持ちが整っていないまま始めると逆効果になることも。とくに成績は良くても「勉強に縛られすぎて疲れている」子は多く、無理に勉強を進めると勉強嫌いになってしまう恐れがあります。
4. 私立の中高一貫校だからこそ、不登校から戻るのは難しいのでしょうか?
戻るのが「難しい」というより、構造的に「戻りにくく感じる」仕組みがあるのは事実です。クラス替えがない、同学年が固定、内部進学制度の影響などがそれにあたります。ただし、正しい支援とタイミングを押さえれば、戻ることは十分に可能です。
5. 小学校では問題なかったのに、中学で突然不登校になるのはなぜ?
小学校では「自然とポジションが確保できていた」子も、中学では「自分で説明しないと居場所ができない」構造になります。学力層が揃った環境で「自分の存在意義」を見失いやすく、アイデンティティの揺らぎから不登校が始まるケースもあります。
6. 子どもが不登校の理由を話してくれません。無理に聞き出すべきでしょうか?
無理に聞き出すのは逆効果です。本人が理由を整理できていない場合も多く、焦って聞き出そうとすると「自己分析できていないのに何か言わなきゃ」と思い、全く違う理由を答えてしまうこともあります。まずは「話せる状態」を作ることが先です。
7. 小学校で不登校でしたが、中学でもまた不登校に…。この先どうすれば?
再発ケースは「また同じことが起きた」のではなく、「新たな適応課題」が表面化したものと考えた方が自然です。過去の経緯を活かしながら、新たなステージに合わせた支援計画を立てていく必要があります。一過性ではない可能性が高いので専門家に相談して根本的な分析が必要です。
まとめ:私立中高一貫校の不登校、焦らず“正しい理解”から始めましょう
中学1年生で不登校になることは、決してめずらしいことではありません。特に私立中高一貫校では、公立とは異なる“見えにくい構造”が背景にあります。
・受験で限界を迎えていた心と体
・小学生時代の“守られたポジション”からの喪失
・自己管理という壁にぶつかった反動
・「これからが本番」という現実へのギャップ
こうした要因は、単なる「燃え尽き」や「合わなかった」では片づけられない深いものです。だからこそ、最初の見立てがとても重要になります。
勉強の遅れは取り戻せる。でも、「勉強嫌い」のこじれは深刻です
私立中学の不登校で多いのが、「勉強が嫌いになってしまった」ケース。これは、勉強の内容そのものよりも、「できていた自分しか認められなかった」自己イメージが崩れたことが原因です。
勉強の遅れは取り戻せます。でも、「嫌いになってしまった勉強」をもう一度やる気にさせるのは、ずっと難しい。だからこそ、早めの支援と「焦らず丁寧な再構築」が必要です。
私立に行かせたことは、決して間違いではありません
不登校になったことで、「私立に行かせなければよかったのかも」と悩む親御さんもいます。でも、実は私立中高一貫校には“再起のチャンス”がたくさんあります。
・高校受験がない → 時間的な余白の中で再構築ができる
不登校支援は、大きく二つのパートに分かれます。「再登校支援(学校に戻れない状態を解除する支援)」と「継続登校支援(学校に戻れたあと適応し継続して登校できるように支援する)」の二つです。
継続登校支援では、時間をかけてきちんと適応できる期間と失敗できる期間を取ってあげることは、子どもたちの負担を軽減します。
公立の場合高校受験期間というパートがあるため、中学三年生の時間中学校での適応期間として子どもたちに使ってあげることが難しいのです。
ところが、内部進学のチャンスがある中高一貫校の子どもたちには、中学三年生の1年間をしっかり中学での適応期間として使ってあげることができるという大きなメリットがあるといえます。
・内部進学が可能 → 成績回復に焦らず“今”を立て直せる
・学力の土台がすでにある → 本人の本来の力は、失われていません
・柔軟な支援制度がある → 個別対応・段階的復帰も可能な場合が多い
・教員との関係性も安定しやすい → 信頼関係を一から築き直しやすい
このように、私立校だからこそ“回復のための環境”が整っているのです。つまずいたのは、力がなかったからではなく、支援の仕方が違っていただけかもしれません。
今が最も動きやすいタイミングです
「しばらく様子を見ていたら、半年が経っていた」「もう少し早く相談すればよかった」——こうした声を、これまで何百件も伺ってきました。
焦る必要はありません。けれど、「今」は支援の入り口に立ちやすい時期です。
FHEでは、心理職によるアセスメントと訪問型支援を通じて、本人の心の状態・学習状態・家庭環境を総合的に見立て、無理のない再構築を支援します。
お子さんの「これから」を、今から一緒に整えていきましょう
今のお子さんの状態は、「戻れない」ではなく、「どう戻るかの道筋が見えていない」だけかもしれません。
どうか、「このままでいいのだろうか」と思ったタイミングで、行動してみてください。私立という環境は、「未来を守る」こともできるステージです。
焦らず、でも一人で抱えず。正しい理解と伴走する支援で、きっと子どもは動き出せます。